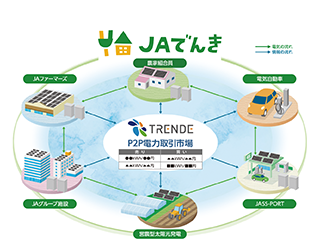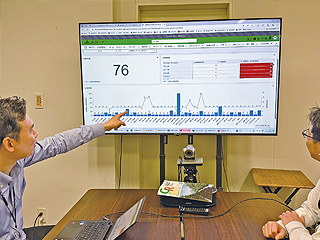連載 食料への権利と農業(3)「耕す市民」の背景を考える 農業ジャーナリスト 榊田みどり

都市農業見直し コミュニティー農園増える
現地事例や識者の見解をもとに、「食料への権利と農業」には何が必要かを考えるシリーズ。第3回は農業ジャーナリストの榊田みどりさんと、世界で広がる「耕す市民」の動きを探ります。
欧米の市街地で農地づくり 「食」へのアクセス強める
2019年に東京都練馬区で開催された「世界都市農業サミット」で、とても印象深かったことがあります。ニューヨーク、ロンドン、トロントなど欧米の都市で、「健康問題(肥満)」や格差拡大の中での「食へのアクセスの公平性」「孤立化の解消(コミュニティー再生)」という視点で都市農業の重要性が語られていたことです。
実際、ロンドンやニューヨークでは、すでに農地も農家もいなくなった市街地に、公共用地などを利用して敢(あ)えて農地を創出し、NPOや自治体が中心となって市民が耕す試みが広がっています。ロンドンでは、2012年のオリンピック開催決定後、開催年までに市内に2012カ所のコミュニティー農園(コミュニティー単位での食料生産プロジェクト)を作ろうという市民運動が誕生。オリンピック終了後も運動は続き、20年には2900カ所まで拡大。行政もこの運動を支援しています。
ニューヨークも、自治体主導で「グリーンサム」事業というコミュニティー農園の設置事業を行っており、2020年段階では550カ所(約40ha)になっています。また、ニューヨーク市住宅公社に農園を設置し、「グリーン・シティ・フォース事業(環境に関わる仕事に従事させる事業)」を活用して低所得の若者が野菜を栽培し、公営住宅の低所得者層に提供する施策を講じています。
一方の富裕層でも、「産業化されたシステムでは新鮮な野菜が手に入らない」と、自家菜園や裏庭養鶏までブームになるなど「アーバン・アグリカルチャー」が広がっています。同サミットに登壇した報告者からは、「コミュニティーの食料プログラムで手に入れることが可能な都市農業の重要性」が指摘されました。
市民が自ら耕すことで「食を選択しアクセスできる権利」を獲得しようというこの潮流。コロナ禍によって経済格差と栄養格差の相関関係が“見える化”した日本でも、遠くない将来、広がるかもしれません。
「農とのかかわりの階段」「地域とのかかわりの階段」を用意する
今年1月、『農的暮らしをはじめる本』を上梓(じょうし)しました。神奈川県秦野市に通って取材を重ねたJAはだのの実践をまとめたものです。
JAはだのでは、都市化が進んだ2000年以降、非農家も参画する交流・観光型の地域農業振興に舵(かじ)を切り、正組合員も准組合員も一体となった「食と農を基軸にした地域に根ざした協同組合」づくりにシフト。05年、新規就農希望者を支援するワンストップ窓口「はだの都市農業支援センター」を設置し、少しだけ農に触れたいひとから新規就農を目指すひとまで、農との関わり方のグラデーションに応じたさまざまな「農の入り口」を用意してきました。
つまり、都市住民が気軽に農の世界に飛び込み、意欲があれば、徐々にステップを踏み、「地域農業の担い手」になることができる仕組みです。就農への最終ステップとなる「はだの市民農業塾(新規就農コース)」を修了し、市内の農地を借りて販売農家になった都市住民はすでに70名を超えています。専業農家、農家レストラン経営、半農半Xと営農スタイルはさまざまで、その多様性も地域の活力になっているようです。
注目したいのは、これら段階的な「農の入り口」が有機的につながっている背景には、JAの地域活動があることです。同JAは、全7支所に「営農活性化推進チーム」を配置し、支所単位で農業生産や農地保全を支援し、新たな担い手の発掘も支所ごとに行う体制をとっています。また、新規就農者など新住民を“地域人”として受け入れる受け皿として、JA生産組合やJA支所運営委員会を地域活動の基盤組織と位置付け、新規就農者や非農家のJA准組合員加入も積極的に推進。今では新住民が生産組合長に就任するケースも登場しています。
JA全農も「91農業」を打ち出しましたが、「多様な担い手」と従来の「担い手(認定農業者・農地所有適格法人)」との連携が求められる昨今、JAグループも、そのための具体的な仕組みづくりが必要ではないでしょうか。